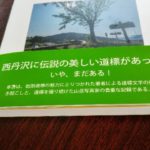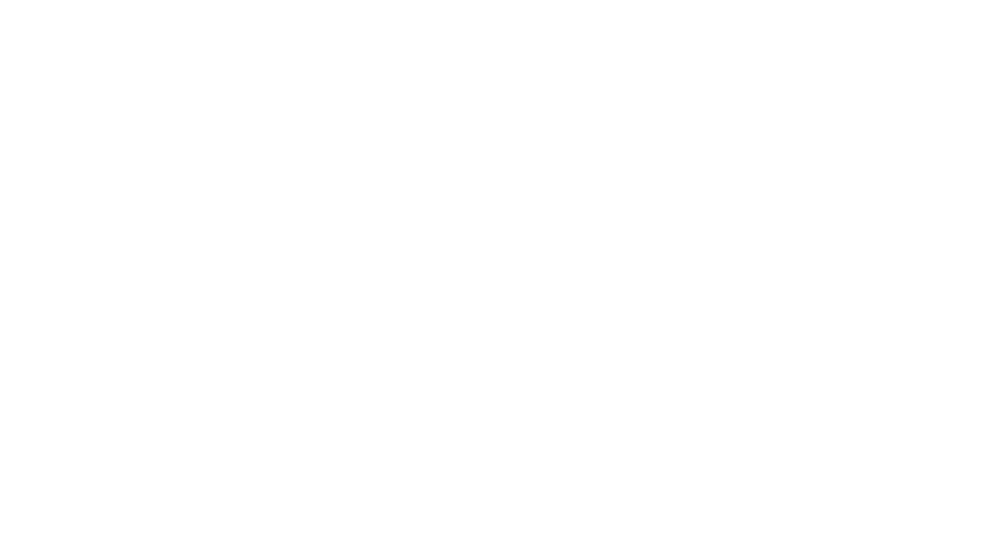皆さま、こんにちは!愛し合っていますか?
今日、ふと思った。
よく、子ども時代に自分の感情を抑圧したために大人になってから問題が起きる人について、「子どもを十分にやってこなかった」などと表現する。
このことについて、私は、「何らかの事情で、子ども時代に。十分に大人(多くは両親)に甘えることができなかった」ことだと定義していた。そして、自分もそのうちの1人であり、父が早くに亡くなったために、自立が早まり、父はもちろん母にも甘えることができなくなった、むしろ、母や弟など周囲を支える側に回ったために、子どもができなくなった、と解釈していた。
これも、決して間違いではないのだけれど。
今日、感じたのは。
「子どもを十分にやってこなかった」というのは、甘えたりワガママを言うことが不足していたというだけではなくて、
子どもが、世界を見て次々と目まぐるしく変わる自分の感情を、両親などの大人に理解して欲しくて拙いなりに精いっぱい表現しようとしていることを、大人から受け止めてもらう経験、あるいは、大人が大人の事情によって子どもの表現を100%受け止めることができなくても、大人なりに理解しようとしてくれて、受け容れようとしてくれていることが伝わるような、ハグや側に居てくれる経験、そういった経験が不足していることを指すのではないか、ということだった。
単に子どもの欲求に基づく要求を叶えてもらうためだけに、大人がいるわけでは、ない。
もちろん、乳幼児期には、食べる、眠る、排せつする、といった生存のための要求を叶えてくれる大人が必要ではあるし、それも愛なのだけれども。
その後、両親やきょうだいとの人間関係から社会化が始まり、感情を認識するようになり、成長するにつれ、子ども時代に自分の感情を表現し大人から自分を十分に受け容れてもらったという経験がある人ほど、自己肯定感が高く、何事にも前向きに取り組むことができるように思う。
私は、その筋の専門家では全くないので、自分の経験や知見に基づく推測に過ぎないけれども。
そういう意味では、私は、少なくとも思春期以降に関しては、自分の気持ちを母に受け止めてもらってきたと思う。
ここ最近、私の中で、子どもの頃の私の幼少期の母に対する恨みつらみ(笑)が出てきていたので、「私、子どもを十分できなかった!」と若干、いや、かなり、被害者意識を持っていたけれど。
確かに、子どもの頃の私には、大人の気持ちに配慮し過ぎたり、大人になろうと背伸びし過ぎた側面も、あったと思う。
けれども、ここまで社会生活を何とか営んでくることができたのは、やはり、母に受け止めてもらった経験があったから、だから人を信頼できたからなのではないかな、と思う。
人間って、複雑だ。
でも、だから、面白いのかもしれない。