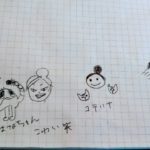小説家の山本文緒さんが膵臓がんで亡くなった、というニュースを知ったのは、11月のある日、友人がFacebookでシェアした記事からだった。58歳の若さだった。
折しもその頃、小説家の瀬戸内寂聴さんも亡くなった。
世代も生き方もずいぶんと違うけれども、2人とも「女の業」を描いた女流作家という点では共通していると思う。
山本文緒さんは、私のちょうど10歳上で、25歳で少女小説でデビューし、30歳のころから一般小説を書き始めた。
私が彼女のことを初めて知ったのは、最初の(次もあるかもしれないのであえてこう言わせて頂く(笑))結婚生活を送っていた大分市のとある書店で、平積みされていた『恋愛中毒』をふと手に取ったのが最初だったように思う。『恋愛中毒』の初版は1998年11月に発売されたそうだから、おそらく1999年か。結婚して1年と少しが経ったころだ。
私は、1人気に入った作家さんができるとほぼ全作品を読破するという癖があり、このため、自分にとっての新規の作家さんに手を出すことは平均的な読書好きの人より腰が重いように思う。
殊に、弁護士になってからは小説を読む時間が激減したためその傾向が顕著であるが、それはさておき。
新規の作家さんの作品をあまり読まないほうであるにもかかわらず、『恋愛中毒』は、いわゆるジャケ買いというかタイトル買いであった。
タイトルが目に飛び込んだ瞬間に、「買う」と決めていた。
しかも、普段の私は文庫派であるにもかかわらず、分厚いハードカバーを久しぶりに買った。『ノルウェイの森』以来だったかもしれない。
当時、私は、夫との関係で悩んでいてその悩みが顕在的には人生のほぼ全てを占めていた。私は、まだ若くて、父が早逝した影響で結婚生活というものへの現実的理解が少なくて、恋愛気分を引き摺っており、自分の心の内を深く見つめることもしないままであったので、夫との恋愛時代に対する自分の執着心を捨てきることができなかった。
もちろん、恋人のような夫婦であっても良いし、恋人と夫婦は異なっていても良いのだけれど、当時の私は、自分がどうしたいのかも理解しておらず、ただただ、「2人でいるのに寂しい」という自分の感情に振り回され、しかもそれを自分の責任とは思わず彼の責任であると思い込んでいた。まさに「恋愛中毒」状態だった。
(なお、いうまでもなく、人間関係はフィフティ・フィフティだし、今の私のポリシーで言えば100パーセント自分の責任だ。「世界は自分が創っている」のである。)
-どうか、どうか、私。これから先の人生、他人を愛しすぎないように。他人を愛するぐらいなら、自分自身を愛するように。(山本文緒・『恋愛中毒』より)
今この文章を読むと、前段の「他人を愛しすぎないように」には疑問符が着くが、後段の「自分自身を愛するように」には深く共感する。
けれども、当時の私は、そこそこ傷ついていたので、「他人を愛しすぎないように」の方に共感してしまった。自分を愛することには、注目することができなかった。
すなわち、心理的には、自分の中の元夫に対する愛情を抑圧し、かつ、自分自身も愛さず、自分への愛も抑圧するということになった。自分の内側を投影だと考えれば当然のことなのだけれど。
そして、抑圧された、本当は自分も相手も存分に愛したい、という内側の愛情エネルギーは出所を失って爆発し、私自身も元夫も傷つける結果となった。
まずは惜しみなく自分自身を愛し、そして、惜しみなく他人を愛する。
それだけのことなのに、なんと難しいことか。
齢49歳になってさえ、難しいと思う。
話を山本文緒さんに戻すと、
『恋愛中毒』以後、私は、山本文緒さんの作品を貪るように読んだ。
『きっと、君は泣く』『あなたには帰る家がある』『ブルーもしくはブルー』『眠れるラプンツェル』『ブラック・ティー』『絶対泣かない』『群青の夜の羽毛布』『みんな行ってしまう』『シュガーレス・ラヴ』『紙婚式』『落花流水』『ファースト・プライオリティー』・・・・そして、エッセイ集。
切なさや苦さや冷酷さや抑圧やその反動としての狂おしさや情熱の発露といった女性の心理描写に長けていて、ほろ苦かったり厳しかったりしんどかったりする結末の作品も多いけれども、どこかに作者の人間愛が垣間見えるところが好きだった。
山本さんがうつ病になり、寡作の人になってからも、これらの作品は私の手元に常にあった。
しかし、弁護士になり、何度かの引っ越しを繰り返すうち、山本さんに限らずだが小説作品は手元から減っていった。
今さきほど確認したら、私の書棚に、山本さんの作品は、なんと短編集の『ファースト・プライオリティー』の文庫しかなかった。
自分のことなのに、驚いてしまった。
処分した意識はあったけれど、たった1冊になったとは思わなかったし、ハードカバーである『恋愛中毒』は持っているのではないかと思っていたからだ。
山本作品がどうのというわけではなく、おそらく、私の離婚前後の記憶や感情が山本さんの作品には紐づいていて、無意識のうちに遠ざけてしまったのかもしれない。
自分の実生活において人間の業を垣間見る機会が増えそのことを重く重く受け止めていたがゆえに、無意識のうちに似たような傾向の山本作品を遠ざけ、フィクションの世界に明るさや救いを求めたのかもしれない。
おそらく、その両方だろう。
今、こうして、山本文緒さんが亡くなり、新作が生まれることはもうないという事実は、いちファンに過ぎない私ですら悲しいことだけれども。
このタイミングで山本文緒さんの作品を思い出したことは、私の人生において、降り始めの雨がぽつりぽつりと数滴身体に落ちてきたような気づきの意味があると感じている。例えば、元夫に対する罪悪感を手放す時なのかもしれない、とか、自分の寿命に対して私は生ききっているのだろうか、とか。
作家に限らず作品を創作するという仕事は、こうして、生命が途絶えても作品は残り、見ず知らずの受取り手に対して影響力を残していく。
使い古された陳腐な表現だが、作品は生き残る。
ここに、クリエイターの醍醐味の1つがあるように感じる。