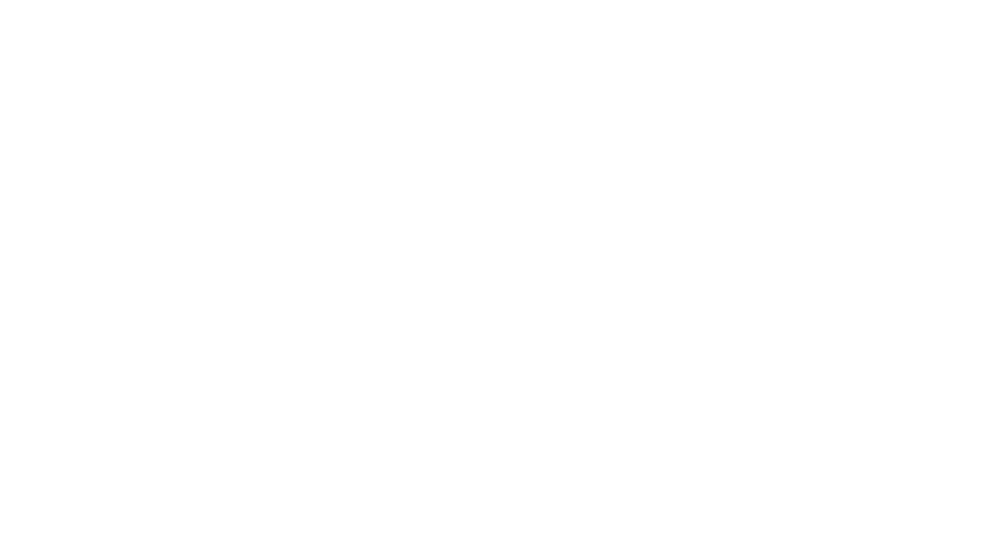皆さま、こんにちは!愛し合っていますか?
たまに戦う弁護士&心理カウンセラーの小川正美です。
前回の記事の続き、「あなたが過去、最も充実感を味わった出来事を、一つ思い出して、その時のことを自伝風に、出来る限り詳しく書いてください。」という宿題の後半です。
—————————
入学して間もない5月ころ、母がまた胸の痛みを訴えて、救急搬送されました。
今度は、循環器だけではなく消化器も調べる、ということで、念入りな検査が行われました。
結果は、胆のうがん。腫瘍の大きさは10センチほどで大きいけれども、他に転移していなければステージ3ということで手術可能、とのドクターの説明でした。
まさかそんなことが、と大きなショックを受けた私と弟でしたが、インターネットで国立がんセンターなどの情報を調べまくり、胆のうがんの術後の予後は良い、5年生存率は当時でたしか90%程度と知り、気持ちを前向きに切り替え、母を支えることに専念しよう、と決意しました。
そこから、母の検査漬けの日々が始まりました。
結局のところ、肝臓に転移が見つかり、ステージ4であり、手術は不可能との診断になりました。
夏ごろのことでした。
ロースクールの前期試験があったころだった記憶です。
それでも、当初は、母も希望を捨てず、抗がん剤が奏効することを期待して、何種類かの抗がん剤を試しました。
温熱が良いと聞いて、夏でも湯舟に長く浸かるようになりました。
今にして思えば、自然療法などもっとたくさんの手段を試せば良かったのですが、当時の私には考えが及びませんでした。
抗がん剤は、母の体力を奪い、次第に気力も奪っていきました。
そもそも、前年に会社を退職した時点で、それまで主に会社での仕事に注力していた母は、燃え尽きたようになっていました。
旅行を薦めても積極的にならず、趣味の俳句も当時はあまり積極的ではありませんでした。
今にして思えば、母は、父が亡くなってから23年、働きづめで苦労して子育てもして、もう父に会いたかったのかもしれません。
秋が深まる頃には、母は、朝夕に起き上がることもつらく、トイレや入浴以外はベッドに臥せっているようになりました。
時折、自宅に伯母や叔母や会社員時代の友人知人が訪れると、元気を振り絞って居間に座っていました。
食欲も落ち、特段制限はありませんでしたが、病院指定の液体状の栄養食品(ひどく不味いもの)を義務的に摂取して命を繋いでいるようになりました。
当時、弟は結婚していましたが、私は離婚して母と2人暮らしでしたので、母は、自分が死ぬと、不安定な身分の私が精神的に生きていけないのではないか、と心配したようです。
実際、私と母は、父が亡くなって、私が大学に入学してある程度の大人になってからは、友達母娘のように仲良くしていました。
話も合うし、性格も似ている。お互いの友人も家に連れてきて、私は母の友人たちとも飲むし、母も私の友人たちと飲む、そんな関係でした。
私が初めての転勤で寂しいと電話した時、別居するかどうか迷っていた時、離婚する時、いつでも暖かく迎えてくれ、抱きしめてくれたのは、母でした。
そんな濃い関係の母娘でしたから、母が私を心配したのも無理はないのです。
秋が深まり、冬が訪れ、母の具合はどんどん悪くなりました。がんによる身体の痛みも出てきて、腹水が溜まり、毎日発熱していました。
「2006年のドイツワールドカップを観戦する」「桜を見る」「そごう美術館の展覧会に行く」そんな目標も、もしかしたら叶わないかもしれない、と思いました。
年が明け、ある時、母は、「もう入院したい」と言いました。
私は、母が、死を覚悟した、と感じました。私も、母の死を覚悟しなければならない、とも。
ロースクールの後期試験が迫っていました。ここで試験を受けないでいると、単位を落とし、留年することになります。
私は、休学して、母の看病に専念するかどうか迷いました。弟や伯母や叔母にも相談しました。
答えは、休学はするな、でした。
母があれだけ私がロースクールに行ったことを喜んでいるのだし、自分のせいで私が休学するなんてことの方が耐えられない、だから休学はしない方がいい、とのことでした。
私は、その意見に納得し、休学しないことにしました。
母の入院先の病院には、学校の授業が終わった後に通いました。この辺りは記憶がうろ覚えなのですが、毎日ではなく2日に1度くらいだったかもしれません。
母の痛みは相当なものだったようで、入院開始後まもなく、モルヒネの点滴が投与されました。
日が経つにつれ、モルヒネの使用量は増え、それに応じて、母の意識は朦朧としていきました。お見舞いに来てくれた人を認識できないこともあったし、話をしてしても上手く通じなかったり、幻覚を見ているような感じもありました。
それでも、一度だけ、私が病室に入って、母に泣きついた時、母の意識が清明になったことがありました。
まるで、高村光太郎の『智恵子抄』の詩で、智恵子さんがレモンをがりりと噛んだ時のように。
母は、本当に、私のことが心配なんだな、と痛感した出来事でした。
無事に後期試験が終わり、冬休みに入り。
ドクターは何も言いませんでしたが、母は個室に移動しました。看護師さんが言うには、母が夜中に痛みなどで泣き叫んでいるとのことでした。病院に寝泊まりしてもいいのよ、と言われました。
それなのに、私は、最期の日しか、寝泊まりできませんでした。
1人でもうすぐ死にゆく母と向き合うのが、怖かったのです。これは、今でも後悔していること。もちろん、その時の自分なりの精一杯だったのだけれども。
2006年2月の終わりの未明、母は息を引き取りました。
人間の五感で最も最後まで生きているのは聴力だと聞いていましたので、私、弟、伯母、叔母、従兄弟らは、懸命に母に語り掛けました。
これまでとても感謝していること、母が私の母でいてくれて良かったこと、私も子ども産んだら母のような母親になりたいこと、必ず弁護士になること。
それから、私は、当時の恋人や友人たちに支えられ、勉強を続けました。
母が居なくなった実家での1人暮らしは、ツラくて寂しかったけれど、当時の彼がよく来てくれて、一緒にご飯を食べたり勉強したりしてくれて、本当に助かりました。
そして、2008年3月に、私は、ロースクールを卒業し、5月に司法試験を受験し、
同年9月、合格しました。
同年11月から司法修習生になり、翌2009年12月、弁護士登録しました。
合格発表の中に自分の受験番号を見つけた時の喜びは、もしかしたら最初の結婚をした時以上だったかもしれません。
最近、ふと、私は、母の繋いでくれた命のバトンを持っていて、母やその母(祖母もまた早くに夫を亡くし苦労して子育てした人でした)が社会の中で味わったような悔しさ・みじめさをもう誰も感じることがないように、女性が被害者にならず男性も加害者にならないようにするお役目があるのかもしれない、と感じることがあります。
———————————
昨夜この話を書いて、翌朝(今朝)ふと思ったのですが、
自信がなくて強がることはよくあるけれど、
相手が自分に対して傷つくような言動をした際に、嵐が過ぎるのを待とうと事なかれ主義を発動したり、「平和主義な良い自分・正しい自分」「理解したい愛のある良い自分」を発動して穏やかなフリをしたり、自らを下に置いて我慢したりしている時って、相手のことを「めんどくさい・厄介な人」として扱っていて、内心見下していて、実は、自信がないんですよね。
内心見下している、ということは、表面の態度はさておき、心理的には上から目線である、ということです。
上から目線。すなわち、強がり。
本当に自信がある人は、わざわざ上から目線を発動したりしませんものね。
そうは言っても、人間だもの。
イヤなことを言われたり理不尽な態度を取られたら、腹も立つし、悲しいし、最後には自分を責めたりもする。
そうした感情を燃やし尽くすために、怒っていいのです。
めんどくせーな!って。はあ?って。むかつく!って。何なら理屈で責めたって、いい。
その場の一時の、しかも見せかけの平和のために、自分を下げる必要なんてないんです。
他人のコンプレックスを刺激しないように、わざわざ下にいく必要なんてないんです。
だって、私も、あなたも、ものすごく頑張って生きてきたんだから。